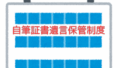制度の概要
死後事務委任契約は、生前に契約を交わし、依頼者が希望したさまざまな手続きを死亡後に代理人に遂行してもらう制度です。相続とは異なる制度で、「故人の遺した意思」を契約により確実に実現する手段として注目されています。
依頼できる内容
具体的には以下のような内容を依頼できます。
葬儀の手配、火葬墓地への埋葬や散骨の希望、行政機関(役所・年金事務所など)への届出、住居の整理・明け渡し、親族や関係者への連絡、病院や施設の清算、公共料金の解約、SNSやオンラインアカウントの削除などデジタル遺品整理、ペットの引き取りや世話の手配
このように、希望に応じて幅広く細かい内容を盛り込めるのが特徴です。
「遺言」との違い
一般的に、亡くなったあとの希望を実現するものとして連想される「遺言」ですが、遺言に関する民法の規定による法的拘束力を持つのは「相続関係」や「身分関係」(相続分や遺言執行者など)に限られます。
「散骨にしてほしい」「樹木葬にしてほしい」「スマホの中身を見ないで消してほしい」などの希望は遺言だけでは強制力がなく、死後事務委任契約によって契約上義務化することで初めて確実に実行できることになります。
必要となるケース
死後事務委任契約は誰でも利用できますが、とくに以下の方には有効です。
「おひとりさま」で頼れる人がいない
身内がいない場合、手続きの主体がいないと行政が対応してくれることも限られます。死後事務を行う代理人の確保が必要です。
家族や親族に頼めない場合
家族が高齢の場合や親族とは疎遠な関係の場合、葬儀や行政への届出、遺品の整理などの煩雑な死後事務を担わせることは難しいでしょう。死後事務委任契約で代理人に行ってもらえるよう準備できます。
家族や親族に負担をかけたくない
上記で述べたとおり、死後事務を行うには手間や時間がかかります。周りに家族や親族がいる場合であっても、遺族に経済的・精神的負担をかけないよう事務委任契約を結ばれる方も多いです。
内縁関係や事実婚の人
法的に関係がない場合、死後事務手続きを断られるなど、行政手続き上で相当に不利になります。死後事務委任契約による代理権付与が有効です。
家族と異なる希望がある場合
宗派や埋葬方法、供養の形式などで家族と異なる希望がある場合、自身の希望をかなえる選択肢として死後事務委任契約をすることが考えられます。
死後事務委任契約で「できること」
以下は、死後事務委任契約でできることの主な具体例です。
葬儀・埋葬に関する手続き
- 遺体の引き取り、葬儀・火葬の手配
- 墓地の手配や散骨の手続き(墓守契約)
- 供養(法要・納骨など)
行政手続きの代行
- 健康保険証・介護保険証などの返却
- 年金受給停止の連絡
- 住民税・固定資産税等の納付・清算
契約・金銭手続き
- 医療費・施設利用料・公共料金の精算
- 賃貸借やリース契約の解約・明け渡し・原状回復
- 不動産・車両の名義変更や返却
関係者への連絡
- 親族や友人への死亡報告
- 口座・契約の整理連絡(葬儀社・保険会社・金融機関など)
遺品・デジタル遺品の整理
- 遺品整理(形見分け含む)
- SNS・LINE・メールアドレスなどの停止・削除
- カード類(クレジット・会員証等)の廃止
ペットの世話
- 飼い主が亡くなった後のペットについて、面倒を見てくれる人への引き渡しや預かり施設への引継ぎ
死後事務委任契約で「できないこと」
死後事務委任契約には、できないこともあります。
相続や身分関係に関する事項はできない
- 相続分、遺言執行者の指定、認知などは「遺言書」でしか指定できません。
生前の財産管理やサポートは不可能
- 生前に契約を結ぶ生前対策ではありますが、死後に実行する契約のため、生前の財産管理や判断・手続きの支援は対象外です。
⇒生前のサポートについては「財産管理契約」「後見制度」「家族信託」等を検討しましょう。
死後事務委任契約の流れ
基本的に以下4ステップで進みます。
STEP 1:依頼内容の決定
何が不安かを整理し、依頼したい項目を明確にします。上記で解説した「できること」を参考に書き出してみることをおすすめします。
STEP 2:代理人(受任者)の選定
死後事務委任を依頼する代理人を決めます。どのような人が候補になるかは、次の「依頼先と特徴」で説明します。
STEP 3:契約書の作成
合意内容を契約書として残します。トラブルを避けるため、条項をできるだけ具体的に記述します。
STEP 4:公正証書化
公証役場にて契約書を公正証書化します。これにより証拠力が高まり、代理人選定の変更等にも対応しやすくなります。
依頼先と特徴
| 依頼先 | 特徴と選び方 |
| ① 友人・親戚 | 資格不要だが信頼関係が重要。遠方や体力の制約を考慮に |
| ② 弁護士・司法書士 | 相続調整の専門家。契約書作成→執行→相続まで一括サポートが可能 |
| ③ 行政書士 | 書類作成に強く、公正証書化に対応。デジタル遺品整理などの新領域に対応可能 |
| ④ 社会福祉協議会等 | 無料または低料金。ただし条件付きのケースが多く、注意が必要 |
| ⑤ 民間企業 (例:イオンライフ) | 提供サービス・費用構成は多様、経営状況に注意 |
死後事務委任契約にかかる費用
公正証書の費用
- 公証人手数料で約11,000円+謄本手数料等で3,000円程度かかるので、1万4,000円程度
契約の執行にかかる費用
- 葬儀・埋葬費用:約100~200万円
- 行政手続きや解約費用:約8~10万円
- デジタル遺品整理等:約1~数万円/件
死後事務委任契約及び公正証書の作成手続きを専門家(司法書士や行政書士等)に依頼した場合には、別途専門家の契約書作成の報酬(10~20万円程度)がかかる
契約執行にかかる金額の目安合計:150〜300万円
<資金準備の方法>
- 執行費用を代理人に預託する
- 死亡時に下りる生命保険金を活用する
- 相続財産から支出する=遺言執行者が預金を解約する
トラブルを避けるポイント
代理人トラブル
- 金銭使い込み⇒信頼性の高い人物・法人を選ぶ
- 代理人の死亡・辞任⇒予備代理人を契約書に明記
契約内容の曖昧さ
- 依頼内容や報酬を明示的に記載すること
- 遺言内容との関係を契約条項に規定(優先順位付け)
民間企業による倒産リスク
- 財務状況や資産保全措置等を慎重に確認すること
相続人・親族とのトラブル
- 死後事務委任契約を結ぶ段階で、事前に内容を共有して了承を得ること
- トラブル発生時の対応ルールなども契約書に明記する
よくある質問
Q. 自治体は死後事務をやってくれますか?
A. 基本的に自治体は火葬・埋葬のみを行います。最近は支援の動きもあり、葬儀や遺品整理に関するカードを預かる取り組みも見られますが、契約の解除や遺品整理など、広範な死後事務を担ってくれるわけではありません。
Q. 契約者にお金がない場合は?
A. 死後事務には費用がかかるため、あらかじめ資金を準備して契約するのが理想です。難しい場合は、相続人に費用の負担を相談したり、死後事務の内容を見直して費用を抑えたり、生命保険の活用を検討する方法があります。
まとめ
死後事務委任契約は、依頼者の意思を生前に確実に実現して後世に安心を届ける契約です。
特に「おひとりさま」「家族と意見が異なる人」「家族や親族に負担をかけたくない人」には有効です。
ただし、相続という場面での問題でもあるため、遺言書や後見制度など他の制度との役割の整理が重要です。したがって死後事務委任契約は、相続全般に関する観点から慎重に内容を検討する必要があります。
そのうえで、依頼内容を整理し、代理人・契約書・資金・親族への合意を準備しておくことがトラブル防止につながります。
専門家の支援を受けながら、将来への不安を安心に変えるステップとして、検討してみてはいかがでしょうか。
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。
遺言書の作成を中心に、様々な生前対策をサポートいたします。どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。
- お問い合わせフォーム
- 公式LINE
- 📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
この記事、どんな人が書いてるのかな?といった関心を持っていただいた方はどうぞ当事務所のホームページをご覧ください!