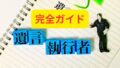「遺言書さえ書いておけば、財産は自分の思い通りに分けられる」・・・そう考えている方は少なくありません。確かに、遺言書はあなたの最終の意思を法的に実現するための大変強力なツールです。しかし、遺言書の「条文」で淡々と財産の分け方を指定するだけでは、その無機的で事務的な条文による指定がかえって相続人間に深い溝を作り、「争族」を引き起こしてしまうリスクすらあることをご存存知でしょうか?
特に、法定相続分とは異なる財産分配を行う場合や、特定の相続人に多くの財産を渡す場合に、他の相続人から「なぜ?」という疑問や不満が起こり、最悪の場合には「相続人として最低限の取り分」を主張する遺留分侵害額請求に繋がる可能性があります。
そこで今回は、遺言書の「法的な効力」とは別に、家族の絆を守り、円満な相続を実現するために重要な役割を果たす「付言事項(ふげんじこう)」について、その効果的な書き方を行政書士が具体的な例文を交えて解説します。
遺言書の「条文」と「付言事項」の違い
まず、遺言書には大きく分けて二つの要素があります。
条文(本文): 法的な効力を持つ部分であり、財産の分配方法(「誰に何を相続させるか」)、遺言執行者の指定、子の認知、推定相続人の廃除といった、原則的には民法で定められた事項を記載します。この部分に書かれた内容は、法的な強制力を持ち、原則としてその通りに実行されます。
※法的効力を持たない事項(特定の行動への希望や助言など)であっても、遺言者の明確な「意思表示」として条文中に含めて記載されるケースは少なくありません。公正証書遺言でも、公証人が遺言全体の趣旨を明確にするため、こうした記載を調整し、遺言者の意思を忠実に反映した形で作成することも多く見られます。
付言事項: 法的な効力は持ちませんが、遺言者が家族や大切な人たちへの思い、遺言の真意、財産分配の理由、感謝の気持ち、残された家族へのメッセージなどを自由に書き残すことができる部分です。法的な強制力はないものの、相続人たちの心情に深く作用し、相続トラブルを未然に防ぐ上で非常に重要な役割を果たします。
なぜ付言事項が「争族」を防ぐ切り札になり得るのか
ちょっと想像してみてください。あなたは、亡くなった親の遺言書を読みました。そこには、「長男にすべての財産を相続させる」とだけ書かれていました。もしあなたが長男ではない他の兄弟姉妹だったら、どう感じるでしょうか?
「なぜ私には何も無いんだ?」「長男ばかり優遇して…」「親は私のことを大切に思っていなかったのか?」
このような疑問や不満、不公平感や一種の寂しさのような感情などが、相続トラブルの大きな火種となります。遺言書が強力な法的効力を持つからこそ、そこに書かれた内容が相続人の心に重くのしかかり、感情的な対立を生み出しやすいのです。
一方、もし遺言書に、財産分配の理由や、各相続人への感謝の言葉、家族への思いが丁寧に綴られていたらどうでしょう。
「本当に厳しい経営環境が続く中で長男は家業を継ぎ、長年苦労を共にしてくれた。その労いの気持ちを込めて、すべてを託すことにした。けれどもちろん、子どもたちへの感謝の気持ちや愛情に差があるわけではないよ。君たちを育てられたことが私の誇りだったんだ。皆、本当にありがとう。これからも皆で助け合って、仲良く暮らしてほしい。」
このような感じで率直な思いが書かれていれば、たとえ財産が偏っていたとしても、相続人は遺言者の真意を理解して、納得しやすくなります。遺言者の心が伝わることで、感情的なしこりが生まれにくくなるのです。付言事項は、遺言者の最後のメッセージであり、家族の絆を守るための、「切り札」となり得るのです。
付言事項が遺留分トラブルを未然に防ぐメカニズム
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に保障された最低限の取り分です。遺言でこの遺留分を侵害された場合、相続人は金銭での「遺留分侵害額請求」を行うことができ、新たなトラブルに発展することもあります。
相続でもめたくない人が知っておくべき「遺留分」とは? | 横浜の行政書士 KUNIのブログ
このような事態を防ぐ手段のひとつが「付言事項」です。なぜ特定の相続人に多くの財産を渡すのか、なぜ他の相続人の分が少なくなったのか。。。その理由や思いを丁寧に記すことで、次のような効果が期待できます。
- 感情的な納得の促進
遺言者の真意や感謝の気持ちが伝わることで、不満や不公平感が和らぎ、争いに発展しにくくなります。 - 遺留分請求のリスク軽減
感情的に納得できれば、請求に至る可能性が低くなります。仮に請求されても、遺言者の配慮を知ることで、話し合いによる解決がしやすくなります。 - 円満な協議のきっかけに
遺言者からの心のこもった言葉が、相続人同士の協調や理解を促す契機となります。
付言事項には法的効力こそありませんが、相続人の心に訴えかけることで、遺留分トラブルを未然に防ぐ有効な手段となります。
相続人の心に響く!効果的な付言事項の例文とポイント
付言事項に決まった形式はありません。あなたの言葉で、率直な気持ちを綴ることが大切です。以下に、いくつかのケースに合わせた例文とポイントをご紹介します。
ケース1:特定の相続人に多く財産を渡す場合
(例) 「長男〇〇へ。あなたは長年、病弱だった私の看病や、家業を一人で守り続けてくれました。本当に感謝しています。この遺言で、あなたに多くの財産を相続させるのは、その多大な苦労と貢献に対する私のせめてもの感謝の気持ちです。弟□□や妹△△△は、このことに不公平を感じるかもしれませんが、どうぞ私の真意を理解して、皆で協力し合って、〇〇を支えてあげてください。当たり前だけど、子どもたちへの愛情は皆同じです。本当にありがとう。」
ポイント:
- 特定の相続人の貢献を具体的に称える。
- 他の相続人への配慮と理解を求める言葉を入れる。
- 他の相続人への愛情が変わらないことを明確に伝える。
ケース2:兄弟姉妹で偏りなく分ける場合
(例) 「私の愛する〇〇、〇〇、〇〇、〇〇へ。あなたたち4人を育てられたことが、私の人生の最大の誇りです。どんな時も、あなたたちの笑顔が私を支えてくれました。お父さんとあなたたちと過ごした日々は、私の宝物です。遺産相続であなたたち4人が喧嘩しないよう、財産は概ね均等に分ける内容でこの遺言書を作成しました。これからも4人仲良く、助け合って生きていってね。お母さんはいつもあなたたちを見守っているよ。」
ポイント:
- 各相続人への愛情を平等に伝える。
- 子どもたち全員で均等分割であることを明確に示し、争ってほしくないという願いを率直に伝える。
- 家族の絆がいつまでも続くことを願う、心温まるメッセージを添える。
ケース3:感謝と労いを伝えたい場合
(例) 「夫〇〇さんへ。長きにわたり、私の人生の伴侶として、どんな時も支え、寄り添ってくれて本当にありがとう。あなたとの日々は、かけがえのない宝物です。あなたと一緒に生きてこられて本当に幸せでした。どうか、これからも身体に気を付けて、あなたの人生を豊かに生きてください。私の分まで幸せになってくれることを願っています。」
ポイント:
- 具体的な感謝の言葉と、相手への労いを伝える。
- 相手の将来を気遣う気持ちを伝える。
ケース4:相続人以外に財産を遺贈する場合(例えば、お世話になった友人や団体など)
(例) 「友人〇〇さんへ。あなたが私を支え、人生を豊かにしてくれたことに心から感謝しています。この遺言で、あなたに私の財産の一部を遺贈するのは、少しでもその感謝の気持ちを形で表したかったからです。子どもたちはどうか私の気持ちを汲み取って、〇〇さんのことを温かく見守ってほしいと願っています。」
ポイント:
- なぜその人に遺贈するのか、具体的な理由や感謝の気持ちを伝える。
- 相続人への理解と受け入れを求める。
付言事項作成の注意点
- 自筆証書遺言の場合、付言も自筆で書く:付言事項を含む遺言全体を自筆で書く必要があります。(別紙の財産目録はPCで作成したり、コピーの添付でもOK.です。)
- 具体的に、しかし感情的に書きすぎない:感情的に書きすぎることは、かえって誤解を生む可能性もあります。冷静かつ誠実に、真意が伝わるように書くことを心がけましょう。
- 特定の相続人の批判や非難をしない:遺言書はあなたの最後のメッセージです。特定の相続人を貶めるような内容は、トラブルを悪化させます。たとえ事実であったとしてもネガティブな言葉は避けましょう。
- 法的効力はないことを理解する:あくまでも意思表示や心情的なメッセージであり、法的な強制力はないことを認識しておきましょう。
まとめ:人生のラストシーンを、自分らしく
遺言書は、単に財産を分配する法的な文書ではありません。法的な効力を持つ条文で財産を正確に指定しつつも、付言事項であなたの感謝の気持ち、真意、そして家族への深い愛情をしっかりと書き残すこと。これこそが、あなたの遺志を円満に実現し、残された家族が互いを思いやり、「争族」ではない「想族」へと導く、最も効果的な方法です。
せっかく遺言書を作るなら、付言事項であなたの「心」も一緒に残しましょう。それが、未来の家族の笑顔を守る、最高の贈り物になるはずです。
『自分らしく生きた人生のラストシーンを、自分らしく締めくくるために。』
「遺言書の作成」や「付言事項の書き方」について、この記事が参考になれば幸いです。
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。
行政書士ながお事務所は、お客様一人ひとりの想いを大切に、最適な遺言書作成をサポートいたします。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
- お問い合わせフォーム
- 公式LINE
- 📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
「遺言書作成サポートの料金」「遺言書Q&A」「遺言書を作成しておいた方が良い場合」などを掲載しています。ぜひ当事務所のホームページをご覧ください