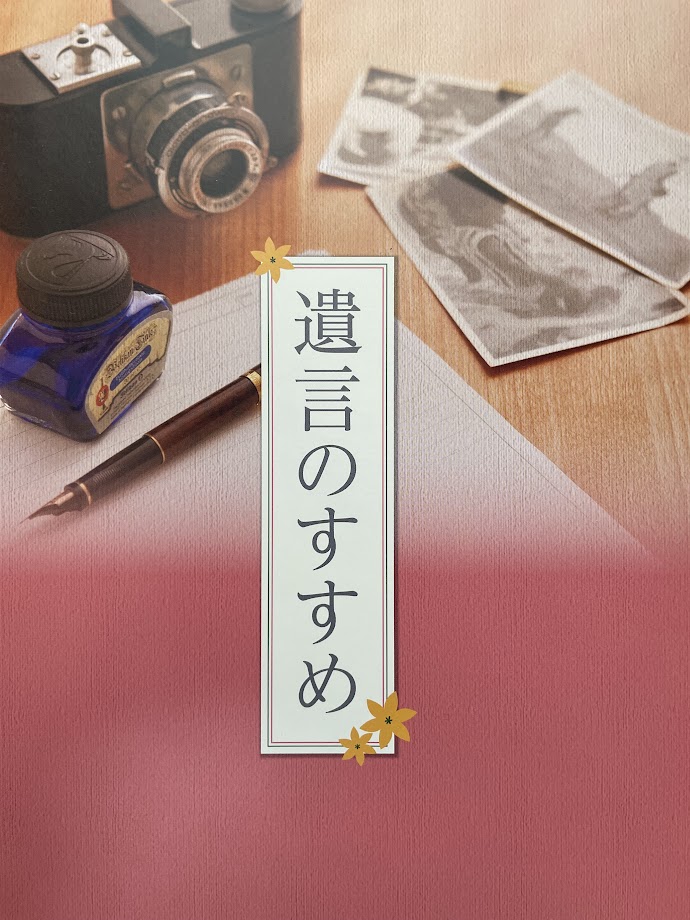遺言書は、誰にでも必ずやってくる未来に対する意思表示であり、残されるご家族への穏やかな相続を願う思いやりです。相続に関しては、遺言書があるかないかで、相続人の間での手続きの煩雑さや精神的な負担が大きく変わります。相続トラブル、いわゆる「争族」を避けるためにも、遺言書はとても重要な役割を果たします。
ここでは、行政書士として遺言・相続の相談を数多く受けてきた経験から、「遺言書を作成しておいた方が良い代表的な10のケース」について、わかりやすく解説します。
遺産相続で争わせたくないとき
「うちの家族は仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続となると話は別。財産の分配に関して、「言った」「言わない」「そんな話は聞いていない」と水掛け論になるケースは少なくありません。生前にきちんと遺言書を作成しておけば、故人の意思が明確に残り、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。
子どものいない夫婦の場合
子どもがいない夫婦の場合、遺言書がなければ、配偶者のほかに故人の親、兄弟姉妹、さらには甥・姪まで相続人になる可能性があります。特に兄弟姉妹には「遺留分(最低限の相続分)」が認められていないため、「全ての財産を配偶者(妻または夫)に相続させたい」と考える場合は、遺言書による指定が非常に有効です。
誰に何をどれだけ与えるかを明確にしておきたいとき
例えば、会社を継いでくれる長男に事業用財産を、介護をしてくれた長女には自宅を、離れて暮らす次男には預貯金をといったように、それぞれの状況に応じて配分を変えたい場合は、遺言書によってその意思を明確にすることができます。ただし、相続人には「遺留分」がありますので、その範囲を超える指定を行う場合は注意が必要です。
内縁の妻、息子の嫁、孫、など法定相続人以外に財産を渡したいとき
法律上の相続人でなければ、遺産分割協議に参加できません。つまり、遺言書がなければ、内縁の配偶者やお世話になった方に財産を渡すことは原則として不可能です。このような場合には、「遺贈」という形で遺言書に明記する必要があります。
前婚の子どもや認知した子どもなどがいる場合
再婚して現在の家庭を築いている場合でも、前婚の子どもには実の親としての相続権があります。前婚の子どもと現在の配偶者との子どもの両方が相続人となるわけです。ふだん交流がない者同士で遺産分割協議を行うとなると、感情のもつれもあり、争いになる可能性が非常に高くなります。遺言書で具体的な財産の配分を明示しておくことで、トラブルの回避が期待できます。
配偶者がすでに亡くなっているとき
残された子どもたちが相続人になるケースでは、一見問題がなさそうに見えます。しかし、親という力のある「調整役」がいなくなったことで、兄弟姉妹間での意見の相違が表面化し、相続争いに発展することも少なくありません。あらかじめ遺言書で分配方法を決めておくことにより、余計な争いを防げます。
家族の手間や精神的負担を減らしたいとき
遺言書がない場合、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。特に相続人が多い、関係性が薄い場合などは合意形成に時間がかかります。遺言書があれば、遺産分割協議を省略し、スムーズに手続きが進みます。加えて「遺言執行者」を指定しておけば、その人が手続きを代理できるため、相続人の負担は格段に軽くなります。
相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に一人でも行方が分からない人がいる場合、遺産分割協議は進められません。家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任手続きを行う必要があり、大きな手間と時間がかかります。ですが、有効な遺言書があれば、その内容に基づいて相続手続きを行うことが可能となり、問題解決の大きな糸口になります。
自営業・家業をしている場合
個人事業主や家業を営んでいる方が亡くなると、事業用資産(店舗・機械設備・営業権など)が複数の相続人で共有状態になる可能性があります。これでは事業の継続が難しくなります。遺言書で事業を特定の相続人に承継させるよう明記しておけば、事業の継続性を確保することができます。
相続人の人数や財産の種類・金額が多い場合
財産の種類が多岐にわたる(不動産、有価証券、預貯金、株式など)場合や、相続人が多人数にわたる場合には、相続手続きが非常に煩雑になります。遺言書を活用して遺産の分配を明記しておくことで、相続手続きの効率化が図れます。さらに、遺言執行者を指定しておけば、相続人全員の手続き参加が不要となり、遺言執行者が一人で相続手続きを進めることが可能となるため、スムーズに財産の移転を進めることができます。
遺言書作成に『早すぎる』ことはありません!
遺言書は高齢になってから書くもの、病気になってから書くもの、というイメージがあるかもしれませんが、そういうものではありません。むしろ、心も体も元気なうちに、冷静な判断のもとで遺言書を作成することが大切です。
自筆証書遺言、公正証書遺言、それぞれにメリット・デメリットがあります。遺言者の状況や家族間の関係性などに応じて最適な方法を選ぶことが可能です。財産額に応じてそれなりの費用がかかりますが、遺言書に沿った相続を確実に実行できる安心感を持ちたいなら、家庭裁判所の検認が不要で、公証人のお墨付きがあるという意味で法的な不備の可能性を低くできる公正証書遺言がお勧めです。
最後に ~行政書士のサポートを活用しましょう~
遺言書は一度書いて終わりではなく、ライフスタイルや家族構成や遺言者の状況の変化に応じて、見直しが必要になることもあります。行政書士は、遺言書の作成サポートはもちろん、遺言執行や相続手続き全般において、依頼者の不安や悩みに寄り添って課題解決のサポートをします。
「自分にはまだ早い」と思わず、「家族のために何ができるか」という視点で、遺言書について一度真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。遺言書の書き方を行政書士に相談してみたい!と思われた方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
「遺言書作成サポートの料金」「遺言書Q&A」「遺言書を作成しておいた方が良い場合」などを掲載しています。ぜひ当事務所のホームページをご覧ください