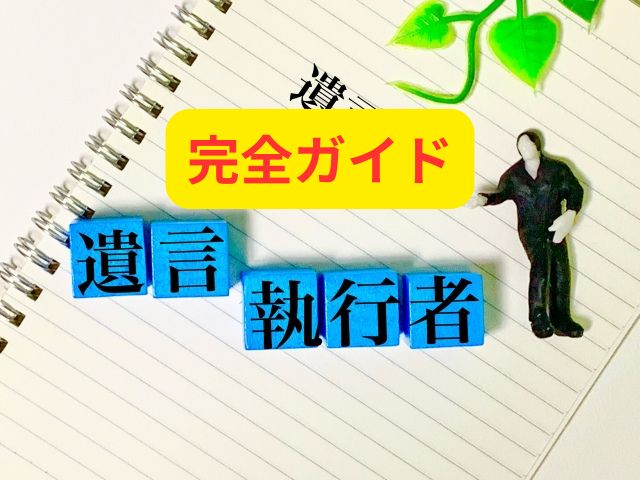「遺言書を書けば相続はスムーズに進む」そう思っていませんか? 実は、遺言書があっても、その内容を確実に実現するためには「遺言執行者」の存在が非常に重要です。遺言執行者がいなければ、遺言書に書かれたあなたの意思は、スムーズに実現されない可能性があります。
遺言執行者とは何か?誰を選ぶべきなのか?具体的に何をするのか?そして費用(報酬相場)はどのくらいか?
これまでも何度か遺言執行に関する記事を書いてきましたが、この記事では、遺言執行者に関するあらゆる疑問をまるごと解決できるよう、詳細に解説していきます。
遺言執行者とは?~遺言を「実現」する専門担当者~
遺言執行者とは、故人の「遺言書の内容を、法的に正しく、かつ確実に実現する」役割を担う人です。相続財産の名義変更や遺産の分配など、多岐にわたる複雑な手続きを、遺言者の意思に従って遂行する「専門担当者」と言えます。
民法によってその権限と義務が定められており、遺言内容を机上の文書から現実の手続きに落とし込んでいく、非常に重要な存在です。
遺言執行者の主な業務は、以下の通りです。
- 財産調査と目録の作成・交付: 不動産、預貯金、株式、車など、すべての相続財産を調査し、正確な目録を作成して相続人全員に提示します。
- 預貯金の払戻し、株式の移管: 金融機関や証券会社とやり取りし、名義変更や現金化の手続きを進めます。
- 不動産や車の名義変更: 法務局や陸運局で、相続人への名義変更手続きを代行します。
- 特定の財産の遺贈・寄付、債務の返済: 遺言書で指定された内容に基づき、個人への遺贈や団体への寄付、あるいは負債の返済などを行います。
- 相続人への手続き完了報告: すべての執行が完了した後、その結果を相続人全員に明確に報告します。
遺言執行者が指定されていない場合、これらの手続きは相続人が協力して進めることになりますが、法的な知識不足や、相続人間での意見の相違、あるいは利害関係が絡むことで、手続きが滞ったり、最悪の場合は相続争いに発展したりするケースが多々あります。
なぜ遺言執行者の指定が必要なのか?
遺言書に遺言執行者を指定しないと、どうなるでしょうか。まず、遺言書の内容によっては、相続人全員の合意がなければ手続きを進められないものが多くあります。例えば、預貯金の払い戻し一つとっても、金融機関によっては相続人全員の署名・捺印を求められることがあり、手間と時間がかかります。
また、遺言書に遺言執行者が記載されていない場合、家庭裁判所にその選任を申し立てることも可能ですが、これには時間も労力もかかります。そして、その間にも相続人同士で意見の対立が深まり、手続きが長引くばかりか、深刻な「争族」に発展するリスクもはらんでいます。
特に、以下のケースでは、遺言執行者の指定が不可欠です。
- 認知や相続人の廃除を遺言で行う場合: これらの手続きは、遺言執行者のみが行うことができます。
- 特定の相続人に偏った内容の遺言: 財産の公平性が保たれない場合、他の相続人からの不満が出やすく、遺言執行者が中立的な立場で手続きを進めることが重要です。
- 財産が多岐にわたり複雑な場合: 不動産、株式、複数の銀行口座など、多種多様な財産がある場合は、専門知識を持った執行者がいた方がスムーズです。
- おひとりさま、身寄りのない場合: 頼れる親族がいない場合、遺言執行者がいないと、遺言書があってもその内容が実現されない恐れがあります。
遺言執行者には誰がなれる?
遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ、基本的には誰でもなることができます。大きく分けて「家族や親族」と「専門家(士業)」の2種類が考えられます。
| 種類 | メリット | デメリット |
| 家族や親族 | 無償でできる場合が多い、故人の意思が伝わりやすい | 煩雑な手続き、法的な知識不足、他の相続人との対立 |
| 行政書士 | 手続きに精通、相続人間の中立性を確保 | 費用がかかる |
| 司法書士 | 手続きに精通、相続人間の中立性を確保 | 費用がかかる |
| 弁護士 | 法的トラブルや遺留分侵害額請求に対応可能 | 高額な費用がかかる |
特に、相続人間の関係が微妙な場合や、相続財産が複雑な場合は、最初から専門家である行政書士や司法書士、弁護士に依頼する方が、トラブルを未然に防ぎ、安全かつ円滑に手続きを進めることができます。
遺言執行の具体的な流れ
遺言執行者が指定された場合、その具体的な流れは以下のようになります。
- 戸籍類・遺言書の確認: 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍・住民票などを収集します。自筆証書遺言の場合、通常は家庭裁判所での「検認」が必要ですが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は検認が不要です。公正証書遺言も検認は不要です。
- 相続人全員への遺言内容通知: 民法第1011条に基づき、遺言執行者は相続人全員に対し、遺言の内容と自身の就任を通知する義務があります。この通知を怠ると、後々トラブルや責任追及の原因となる可能性があるため、大変重要です。
- 財産調査と目録の作成・交付: 預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、債務(借金)などのマイナスの財産もすべて調査し、正確な財産目録を作成します。この目録は、相続人全員に交付します。「知らない財産」が後から発覚するケースも多いため、専門家による照会が有効です。
- 名義変更・財産の引き渡し: 財産目録に基づいて、具体的な執行業務を進めます。預貯金の解約・払い戻し、不動産登記の名義変更、車の名義変更、株式・証券の移管などを行います。金融機関や法務局の書類は相当に複雑で、不備があると何度も出直しになるため、専門知識が必要です。
- 相続人への完了報告: すべての名義変更や財産の引き渡しが完了した後、遺言執行者はその内容を詳細に記録し、相続人全員に対して完了報告を行います。これをきちんと行わないと、相続人間の不信感や後日の紛争に繋がることがあります。
遺言執行でよくあるトラブル事例
遺言執行は、法的な知識だけでなく、実務的な経験が求められます。実際に起こりやすいトラブルには、以下のようなものがあります。
- 隠し口座・隠し資産が発覚: 遺言者が生前に伝えていなかった財産が後から見つかり、手続きが滞る。
- 相続人の一部が音信不通: 遺言内容の通知や手続きの協力が得られず、執行が進まない。
- 遺留分請求が突然届く: 遺言内容が特定の相続人に偏っていた場合、遺留分権利者から遺留分侵害額請求が届き、紛争に発展する。
- 相続人間で財産目録の内容に異議が出る: 評価額や記載内容について納得がいかず、話し合いが平行線を辿る。
こうした場合、遺言執行者が専門家であれば、冷静に状況を把握し、迅速に対応し、必要に応じて弁護士など他の専門家とも連携して解決へと導くことができます。
遺言執行者の報酬相場
遺言執行者の報酬は、遺産総額や業務の複雑さによって変動しますが、一般的には以下の目安となります。
- 遺産総額の1%前後~2%が多くみられます。
- ただし、遺産総額が少なくても、最低報酬額として30~50万円程度が設定されている事務所が多いです。
- 相続財産が多岐にわたる場合や、相続人間で調整が必要な複雑な案件では、別途費用や加算が生じる場合があります。
例えば、遺産総額が3,000万円の場合、報酬は目安として約30~60万円程度、1億円の場合、100万円は見ておく必要があります。
家族を遺言執行者にする場合の注意点
遺言執行者を家族や親族に依頼する場合も多いです。その場合は、以下の点に注意し、備えておくことが大切です。
- 無理だと感じたら専門家に委任して良いことを伝えておく: 遺言執行は専門性と手間がかかるため、家族が困難を感じたらいつでも専門家に頼れるよう、事前にその意思を伝えておきましょう。
- 遺留分侵害額請求がきたら迷わず弁護士に相談するよう助言する: 家族だけでは対応が難しい法的トラブルに発展した場合の対処法を明確にしておきます。
- 財産リストや戸籍類を遺言者が生前に準備しておく: 家族の負担を軽減するため、事前に財産の一覧を作成し、戸籍などの必要書類をできる限り収集して整理しておくと、遺言執行が格段にスムーズになります。
まとめ 遺言執行は「周到な準備」と「確かな遺言執行者」で決まる
遺言書は「書けば終わり」ではありません。書かれたあなたの意思が、いかに滞りなく、そして円満に実現することができるかを考えてこそ、真に意味を持つのです。
だからこそ、誰を遺言執行者に指定するか、そして、その執行者があなたの意思を確実に実現するために、どのような準備をしておくかがとても重要です。信頼できる遺言執行者の指定と、ご家族への事前の情報共有が、トラブルのないスムーズな相続への鍵となります。
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。
行政書士ながお事務所は、お客様一人ひとりの想いを大切に、最適なサポートいたします。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
- お問い合わせフォーム
- 公式LINE
- 📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
この記事、どんな人が書いてるのかな?と思われた方は、当事務所のホームページへ!