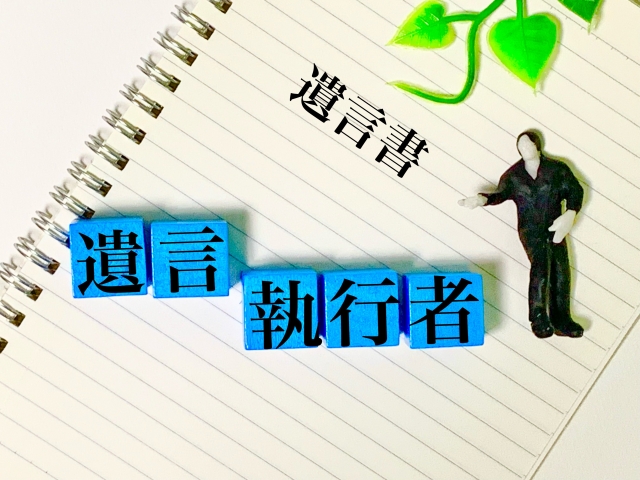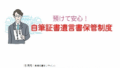遺言書を作成するとき、「遺言執行者」という言葉を耳にする方も多いのではないでしょうか。遺言執行者は、被相続人の遺志を実現するために重要な役割を果たします。今回は、遺言執行者の意義や役割、誰がなるのか、指定された場合の手続き、そして行政書士などの専門家に依頼した場合の費用感まで、幅広く解説します。
遺言執行者とは?
「遺言執行者」とは、被相続人の遺言内容を実現するために、相続財産の管理や名義変更、分配など、遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を持つ人をいいます。平たく言うと、「遺言書を持って手続きに走り回る人」です。
遺言書に書かれてある内容というのは、遺言者本人が亡くなると自動的に不動産の名義が変わったり、預貯金が解約されて払い戻されるわけではありません。誰かが遺言書の内容を実現するための行為をする必要があります。
遺言執行者は必ずしも指定しなければいけないというわけではありませんが、指定されている場合とされていない場合とでは手続きが大きく異なってきます。例えば、不動産を第三者に遺贈する場合に遺言執行者が指定されていないと、登記の際に相続人全員の署名捺印が必要になります。
基本的に遺言書に基づいて預貯金の解約や不動産の名義変更を行うには、遺言執行者を選任しておく方が手続きが格段にスムーズに進みます。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、遺言書に記載することによって遺言者が指定することが多いですが、指定がない場合は、相続人や遺贈を受けた人などの利害関係人が家庭裁判所に申立てることで選任することもできます。
遺言執行者には、未成年者や破産者でなければ誰でもなることができますが、実務上は相続人か専門家のどちらかがなるのがほとんどです。
相続人を遺言執行者に指定する場合は多いのですが、遺言書の内容に不満を持つであろう相続人を遺言執行者に指定するのは良くありません。あまり財産をもらえないのに、あちこち手続きに走り回らないといけないというのは、相続人間のトラブルの元凶になります。相続人を遺言執行者に指定する場合には、遺言書で多く相続させる人を指定しておくことです。
また、弁護士や行政書士などの専門家を指定することで、遺言執行がスムーズに進められやすくなります。ただ、専門家を指定する場合は相続財産の中から報酬を支払うことになるため、遺言執行者の専門家と協議のうえで遺言書に報酬額等を記載しておくことをおすすめします。記載がない場合、報酬額等を相続が発生してから相続人との協議で決めることになりますが、そこで揉めるケースがよくあります。
遺言執行者の法的地位と権限
かつて遺言執行者は「相続人の代理人とみなす」とされていましたが、現在ではその地位が明確化され「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められました。
少し難しい表現になりますが、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる」ものとされています。つまり遺言執行者は、遺産の状況を調査し、遺産を管理し、遺産を相続人に分配する権利を有し、相続人の利益・不利益にかかわらず、遺言執行者の行為の効果が相続人に帰属することになります。
遺言執行者は、相続人の利益を実現するのではなく、遺言者の真の利益を実現する地位にあるということです。
そして、相続人は、遺言の執行を妨げる行為をすることができず、これに違反した行為は、無効となるものとされています。
遺言執行者の主な職務と義務
遺言執行者の職務は多岐にわたり、以下のような義務があります。
任務の開始義務
就任を承諾したときは、直ちにその任務を開始しなければなりません。最初に行うのは、被相続人の戸籍謄本等を遡って取得し、相続人を調査・確定する作業です。
就任通知義務
相続人が確定したら、相続人全員に遺言執行者の就任通知と遺言書の写しを送付します。たとえ遺言で財産を一切相続しない相続人がいても、通知義務があります。
相続財産目録の作成・交付義務
遺言執行者は被相続人のプラス財産とマイナス財産を調査し、「相続財産目録」を作成し、相続人全員に交付する義務があります。固定資産課税台帳をまとめた一覧表(名寄帳)や銀行の残高証明書など、多くの書類を収集・整理して作成することになります。
相続財産の引渡義務
遺産の内容が明らかになったら、遺産として判明した金銭や受領した金銭等を相続人に引き渡します。
具体的には、預貯金の解約による金銭の引き渡しや名義変更、不動産の登記名義の変更などです。遺産の移転先は、法定相続人とは限らず、遺言によって財産の贈与を受ける受遺者も含まれます。
報告義務
任務終了後は、遅滞なくその経過・結果を相続人に報告しなければなりません。途中経過についても相続人から請求があれば報告が必要です。
善管注意義務
遺言執行者は、遺言の執行をするにあたり、善良な管理者としての注意義務を負います。弁護士や行政書士などの専門家が就任する場合は、より高い水準の注意義務が求められるといわれています。
その他の手続き
遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現する手続きを実行しなければなりません。その手続きには、認知、推定相続人の廃除や廃除の取消し、生命保険金受取人の変更手続きなども含まれます。たとえば、遺言による認知が記載されている場合は、遺言執行者が、就任の日から10日以内に認知の届出をしなければなりません(戸籍法64条)。
遺言執行者に専門家を指定するメリットと費用感
遺言執行者には相続人を指定することも多いのですが、法律事務が含まれる相続手続きの煩雑さや相続人間のトラブル回避の観点から、弁護士や行政書士などの専門家に依頼するケースも増えています。
行政書士に依頼する場合の報酬は事務所によって異なりますが、相続財産の総額や内容、業務の難易度に応じて、一般的には30万円〜100万円程度が相場です(遺産額が多額の場合はパーセンテージ制を採る事務所もあります)。
遺言執行者に専門家を指定することで、相続人間の公平性を保ちつつ、法律に沿った適切かつスムーズな手続きを進めることが期待できます。
まとめ
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する重要な役割を担っています。遺言執行者の義務と職務の内容は多岐に渡るため、時として相続人間で争いが生じることもあります。
遺言書の作成段階から遺言執行者を指定するのかしないのか、相続人の中から指定するか、専門家に依頼するか、専門家なら誰にいくらで依頼するか等、しっかりと準備を進めておくことをおすすめします。
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。
遺言執行に関する不安がある場合や、遺言書の作成をゼロからしっかりサポートしてほしい場合など、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。
- お問い合わせフォーム
- 公式LINE
- 📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
この記事、どんな人が書いてるのかな?といった関心を持っていただいた方はどうぞ当事務所のホームページをご覧ください!