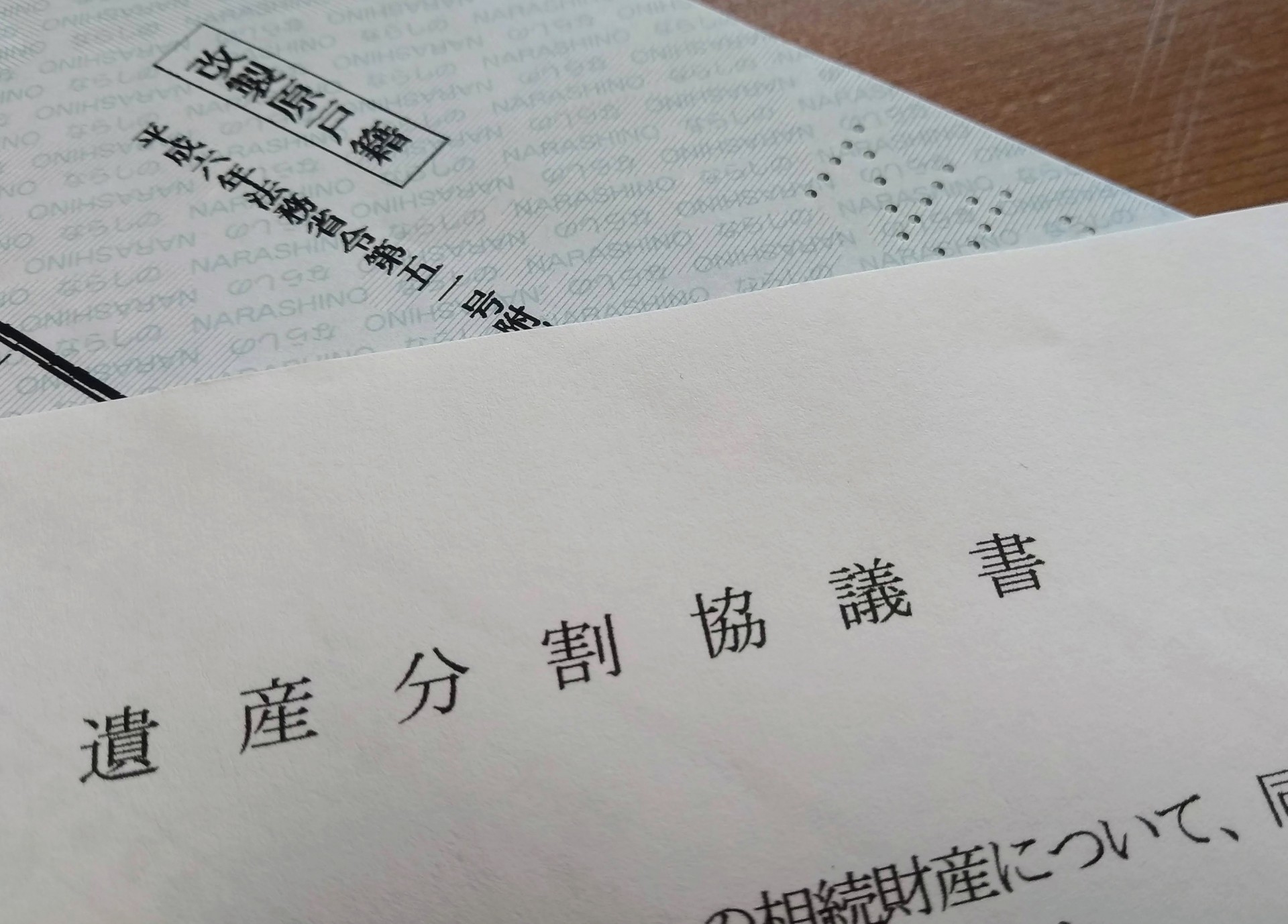こんにちは。遺言・相続専門の行政書士です。
前回の記事では「遺産分割協議って何ですか?どうやって進めるのでしょうか?」というテーマでお話ししました。今回は、その続きとして、遺産分割協議の結果をまとめるために作成する文書である「遺産分割協議書」の書き方について詳しく解説します。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分け方を記録する重要な書類です。不動産の名義変更や預貯金の解約など、具体的な相続手続きを進めるために必要不可欠な書類です。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を文書にした重要な書類です。この協議書には法律上の決まった書式はありませんが、次のような要件を満たしている必要があります。
- 相続人全員の合意があること
- 相続人全員の署名と実印の押印があること
- 相続人全員の印鑑証明書を添付すること
この書類をもとに、法務局等の官公庁や銀行・証券会社などで様々な名義変更や解約手続きを行うことができます。
相続の際に遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞ってしまいます。そして、相続財産を亡くなった方の名義のまま放置すれば、将来、大きなトラブルにつながる恐れがあります。相続する際に遺言書がない場合には、必ず作成したほうが良い書類です。
遺産分割協議書に記載する基本的な内容
遺産分割協議書に盛り込むべき主な項目は、以下のとおりです。
1. 被相続人の情報
- 氏名(亡くなった方)
- 生年月日
- 死亡年月日
- 最後の住所
- 本籍地
2. 遺産分割協議が成立した旨
遺産分割協議書を作成する際は、「誰が相続人となるのか」を明確に記載する必要があります。下記のように、きちんと続柄や氏名を書いて特定し、相続人全員で分割協議をして成立した旨を記載します。
「被相続人〇〇〇〇の遺産相続につき、被相続人の妻△△△△、長男〇〇〇〇、長女□□□□、次男××××の相続人全員で遺産分割協議を行い、次の通りに遺産分割の協議が成立した。」
3. 相続人の情報
- 氏名
- 続柄(長男、次女、夫、妻、など)
- 住所
- 実印で押印
4. 相続財産の内容
遺産分割協議書では、「相続財産の特定」が非常に重要です。相続財産が正しく特定されなければ、遺産分割協議書が意味のないものになってしまいます。
不動産は、登記簿謄本(全部事項証明書)の「表題部」をそのまま書き写しましょう。細かい数字が多いので、間違えないように細心の注意が必要です。
- 不動産(土地):所在地、地番、地目、地積
- 不動産(建物):所在地、家屋番号、種類、構造、床面積
- 預貯金:金融機関名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人
- 有価証券:銘柄、証券会社名、株数、未受領配当金の取扱い、など
- 自動車:車種、登録番号、他、車検証の通りに記載
- 債務・負債:プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記す。債権者、契約内容、債務残高について記載
5. 各相続人の取得分
上記で特定した財産について、各相続人がどの財産をどれだけ取得するか、を記載します。
文章表現は、基本的には「~取得する」とします。権利義務の内容によっては、「~相続する」「~承継する」などいくつかの表現がありますが、適切な表現の選択について心配な場合は行政書士などの専門家に相談してください。
- 次の不動産(土地・建物)については、相続人 長男〇〇〇〇が取得する
- 次の預金については、相続人 妻△△△△が取得する
- 次の有価証券については、相続人 長女□□□□と次男××××が各2分の1ずつ取得する
6. 遺産分割協議書を作成する旨
「以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印のうえ1通ずつ所持する。」
作成上の注意点
● 相続人全員の署名・実印押印と印鑑証明書が必要
一人でも署名や押印が欠けていると、遺産分割協議書は無効になります。必ず全員の署名・実印押印と印鑑証明書が必要です。
● 財産の表示は正確に
特に不動産については、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている情報をそのまま記載するのが原則です。不正確な記載では登記の名義変更ができません。
● 財産及び債務の漏れが判明した場合をカバーする文言
例1)「本協議書に記載のない財産及び債務並びに後日判明した財産及び債務については、全て相続人〇〇〇〇が取得及び承継するものとし、他の相続人は一切異議を述べないものとする」
例2)「本協議書に記載のない財産及び債務並びに後日判明した財産及び債務については、相続人全員がその財産について再度協議を行うこととする。」
など、あとで財産や債務に漏れがあったことが判明したときのために、包括的にカバーできる文言を記載します。
例1)の場合は、再度全員で集まって遺産分割協議をやり直すことなく、指定の通りに相続が実行できるメリットがあります。例2)の場合は、再度の遺産分割協議をすることになりますが、相続人の相続割合やほかの相続の金額によって、基礎控除額をはるかに超えてしまうケースなども考慮して、臨機応変に対応することができるというメリットがあります。
どういった文言が良いかは、ケースバイケースになりますので、心配な場合は行政書士などの専門家に相談してみてください。
● 遺産分割協議書は相続人の人数分を作成する
遺産分割協議書が完成したら、相続人が各自1通ずつ所持できるよう、相続人の人数分の部数を作成します。そして、すべての協議書に相続人全員の署名・捺印が必要です。この遺産分割協議書を使って、各相続人が相続したそれぞれの財産の名義変更を行うことができます。
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリット
相続登記や金融機関の手続き等に対応しやすい正確な書式・文言・記載内容で作成できます。また、専門家は公平・中立な立場で協議書の内容や相続手続きのサポートができます。
遺産分割協議書を共同相続人だけで作成した場合、財産の記載漏れや不備、もしくは表現の曖昧さなどによって、後々の手続き等でトラブルになることがあります。特に相続人が多い場合や、家族関係が複雑な場合、財産が多く多種多様な場合、遠方に住んでいる方がいる場合などは、行政書士などの専門家に相談されるのが安心です。
まとめ
遺産分割協議書は、遺産をどのように分けるかを文書で明確にし、実際の相続手続きにつなげるための非常に重要な書類です。
書式に決まりはありませんが、記載内容の正確性・相続人全員の合意・署名捺印が求められます。不備があると相続手続きが進まず、結果として相続全体の遅延やトラブルにもつながります。
遺産分割協議書の作成に不安がある方は、早めに行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。相続手続きにあたって、「遺産分割協議書の作り方を知りたいんだけど、ネットを見ただけじゃ不安だな。。。」という方は、お気軽に当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。
この記事、どんな人が書いてるのかな?といった関心を持っていただいた方はどうぞ当事務所のホームページをご覧ください!